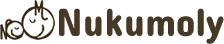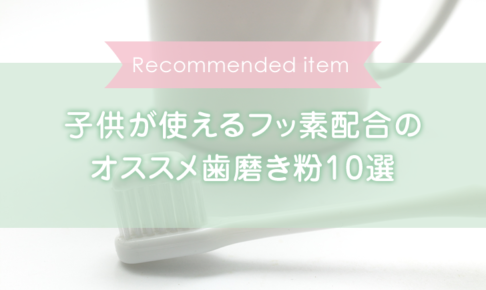小さいうちから歯磨きの習慣を付けることはとても大切です。
そのため、自分でまだ歯磨きができないうちからでも、毎日ママやパパが歯磨きをしっかりしてあげることが歯磨き習慣を付ける一環としても大切なことですが、幼児は歯磨きを嫌うことが多いと言われています。
ここではなぜ歯磨きを嫌うのか、その理由から対策などを考えてみたいと思います。
この記事の内容
子供が歯磨きを嫌がる理由を知ろう
何となく気持ち悪い
子供が歯磨きを嫌う理由はいろいろありますが、その中でも気持が悪いという理由がとても多いようです。
やはり大人でも特に口の中は何か異物を入れることに違和感を感じます。
口はいろいろなものを食べるという場所であり、体の外部と内部をつなぐ部分でもあるのです。
そのため、口はとてもデリケートで、異物など納得できないものを入れることをとても嫌う本能をもっています。
つまり歯磨きについて、大人のように安全性や必要性などまだ分かっていない幼児は、口の中に入れる歯ブラシなどは異物でしかありません。
理由は特にはっきりしていなくても、気持が悪い、不快だという気持に襲われる場合が多いのです。
何となく怖い
気持が悪いという意味と同じ部分がありますが、やはり口に何か納得のいかないものを入れることの恐怖は本能であり、それは小さい子供でも備わっているものなのです。
そのため、怖いものでないということが分かれば、スムーズに歯磨きができるようになります。
とは言っても、ママたちは一生懸命歯磨きの大切さなどを説明するわけですが、それでもなかなかスムーズに歯磨きをやらせてくれないものです。
もう少し大きくなると、「○○だから怖くないよ」という話をすれば子供も納得できますが、まだ幼児の場合はそのような話を聞く前に、自分の怖いという感情が先に立ってしまいます。
そうなったら、もうママの話など聞く余裕などまったくありません。
そのため、幼児の場合は、あまり説明するより歯磨きが楽しいという感情をくすぐるような方法をとると、恐怖はなくなりスムーズに歯磨きをさせてくれます。
一度やったら痛かった
赤ちゃんにとっては、ただでさえ訳の分からない棒のようなものを口に入れられるわけですから、とても怖いし不快である可能性があります。
特に口はとても敏感が高い部分でもあり、本能的にも不安を感じやすいところです。
その上、目の前で行われるのでより恐怖があります。
それでも頑張って歯磨きをしていたときに、歯ブラシが歯茎に当たってしまえば、とても痛い思いをしてしまい、もう幼児にとっては「歯磨き=痛い」ということになってしまうのです。
そのため、ママたちは優しく丁寧に歯ブラシを行うようにしなければなりません。
それでも痛い思いをしてしまったら、その後からは「歯磨き=痛い」ということから「歯磨き=楽しい」などのイメージに払拭していくことが必要となります。
押さえつけられたくない
ママなどが歯磨きを行うときには、どうしても暴れては危ないので軽く押さえながら行います。
しかし、幼児はそれがとても不快であり、余計暴れることになります。
その反動でママも強く抑えてしまうと、もう子供は絶対に嫌だと思うようになってしまい悪循環になってしまうので、まず体を押さえることはやめるようにしましょう。
もちろん歯磨きをしないと虫歯になる

どんな小さい子供でも歯磨きをしなければ虫歯になります。
口の中に残った食物に群がる虫歯菌が増殖して虫歯になるということは、大人となんら変わりはありません。
また、幼児の歯はとても小さいのであっという間に広がってしまいます。
乳歯はどうせ抜けるものだから、永久歯になるまではそんなに虫歯に神経質になることはないと思っている人もいるようです。
しかし、歯の問題ではなく、特に1歳半~3歳の幼児は一番虫歯菌に感染しやすい時期だと言われているのです。
この時期に虫歯菌が口の中の常在菌として住み着いてしまうことで、今後の人生で虫歯になりやすい体質になってしまうという、重要な時期でもあるのです。
そのため、特にこの時期の虫歯菌の増殖は、絶対に避けるべきだと言われています。
子供が歯磨きを嫌がる時の対策例
ママやパパが一緒に歯磨きをする

子供が歯磨きを嫌がる理由を考えても、やはり幼児にいろいろ難しいことを説明するよりも、ママやパパが楽しそうに歯磨きをすることを見せることが一番です。
どんな説明より、ママやパパがやっていることこそ、子供にとっての最高の納得法です。
ママやパパが楽しそうに歯磨きをするところを見せてあげましょう。
極端に言えば踊りながらでもOKです。
子供が興味を持って楽しそうだと感じるようなパフォーマンスを見せてあげます。
そこで「○○ちゃんもやってみようか」と言って、歯ブラシを持たせて一緒に歯磨きをやってみましょう。
もちろん「歯の裏も奥もちゃんと磨いて」なんて野暮なことは一切言いません。
まずは自分でゴシゴシすることを楽しませます。
その後、「きれいに磨けたかな?ちょっと見せてね」と言って、もう一度磨いてあげます。
これで慣れてくれば、自分でゴシゴシした後はママのチェックも問題なくなるはずです。
「おかあさんといっしょ」などの歯磨きの映像を見せる
ママやパパが楽しそうに歯磨きをしているところを見えるという方法だけでなく、「おかあさんといっしょ」のような歯磨きの映像を見せながら、ママもそのときに一緒にパフォーマンスで歯磨きをしてみましょう。
子供はマネをしたがるので、そういった歯磨きの映像を見せることでマネをさせるのも1つの手です。
甘い歯磨き粉を使う
また実際に歯磨きをするときには、子供が好きな甘いフルーツ味などの歯磨き粉を選ぶようにするのも1つの方法です。
大人用は大人が清涼感を感じるためのものであり、子供にとっては刺激でしかありません。
歯磨き粉を使う場合はフッ素などが配合してあるタイプを使うと、さらに虫歯予防に効果的です。
歯磨きはコミュニケーションの一環
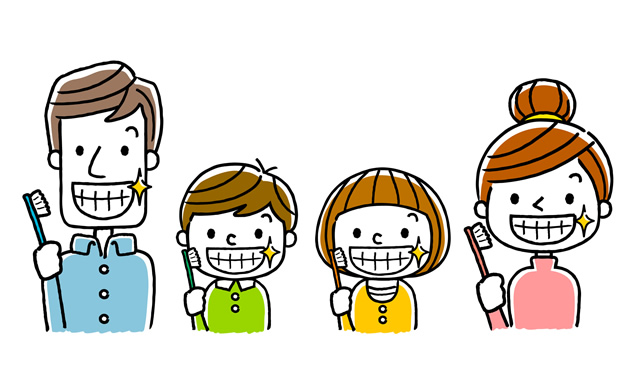
歯磨きはコミュニケーションの一環として行いましょう。
実際はコミュニケーションというより、口内洗浄、虫歯予防、そして結局は健康にもつながる重要な行為です。
しかし、それを上手に習慣として身につけるためには、ママやパパとのコミュニケーションの1つにしてしまいましょう。
虫歯予防、健康維持のためであることは、もう少し分かる年齢になったら、しっかり伝えることも大切です。
この時期に嫌々歯磨きをさせる子供と楽しみながら歯磨きをさせる子供では、大きくなってから歯磨きに対するイメージが違ってしまいます。
大きくなって当たり前のように歯磨きをする子供と、できるだけ歯磨きをサボろうとする子供になる大きな分かれ目でもあるのです。